
最近、着物関連の話題があまり良くない方向で話題になることが多いと思ったので久々にブログを書こうかなと思いましたが、キム・カーダシアン氏の話を取り扱う前に、自分の中の着物という概念の整理をしつつ、着物という言葉の成り立ち、着物の成り立ちを書いておこうと大学時代の卒業論文を引っ張り出してきました。
着物という言葉一つとっても、今回の「KIMONO」の商標問題の際に上がっていた意見を見ていても、人によって、シルク以外は着物ではない。手工芸で作られてもの以外は着物ではない。天然繊維以外は着物じゃない。正統な着こなし以外は着物じゃない。と個々人が考える日本の伝統衣装の着物の概念はそれぞれの定義、枠があるなと思いました。
僕自身の着物の定義はというと、着物という言葉を職務上、対外的に使うときは世間一般で言われる和服としての着物の意味で使っていますが、僕自身の中では、着物という言葉は、礼服の着物もカジュアルな着物やkimono姫のような個性的な着こなしも、さらに言えば、剣道や弓道みたいな道着はもちろん、和風テイストなアパレル製品など結構範囲が広めです。さらに広げるのであれば、着物の元の意味である「着る物」全般(未だにご年配の方は衣類全般を着物という人も僅かながらいる)、下着や靴下であっても広義的な意味では着物と捉えています。
ただ何でも着物だと言うのではなく、狭義的な着物から広義的な着物まで、枠を自由に取り外しして考え、どういった切り口やコンセプトを持って、着物の要素を昇華してるかどうかが、自分の中で着物として言葉を使う一つの基準やデザイナーとしての行動の指針になっています。
今回のKIMONOの商標問題で、初めて着物について考える人もいたでしょうし、自分と他人の着物に対する考え方の違いに戸惑った方もいたと思います。
それぞれ着物に対する思いがあって、自由な着物の捉え方があっていいと思うので、他人の考えを排除するのではなくそういう考え方もあるよねと認めあえれば、そういう多様性がある方が健全やなとおもっています。(うちはインクジェットでプリントしていて、シルク以外にも、中にはセオαとかポリエステルのものも作ることがあるので、一部の人からしたらお前が言うなと言われるかもしれませんが。。。)
今回のKIMONOの商標問題を通じて、意外と着物の歴史は知られていないと感じました。僕も大学時代に京友禅業界をテーマに研究をはじめた際に、まず着物ってなんやねんって思って、着物という言葉の成り立ち、小袖の成り立ちについて調べる前はそうでした。
着物というものを考えるきっかけになられた方も多かった思いますので、着物という言葉の成り立ちや今の着物の原型になった小袖の成り立ちを知りたい方に向けに10年前に書いた学部時代の卒業論文の一部を今回のブログに載せてみようと思いました。
卒論は一見識にしか過ぎませんし、歴史がこうだから着物はこれが正しいという訳でなく、時代や社会や人、それぞれの文脈によって着物という概念も変化するものだと思っております。
僕は僕の立場で、着物の歴史を知って仕事を通して今の着物に対する考えに至っているので、同じ考えになる人様に自分の考えを押し付けるつもりもありません。
自分なりの着物を考えるヒント程度に着物という言葉の成り立ち、小袖の成り立ちについて流し読みしてくれたら幸いです。
※僕の学部時代の卒論のテーマは「京友禅に見る呉服業界の現状と京友禅の将来性」だったので、服飾史が主要テーマではないため、卒論ではあくまで服飾史としては、概要しか取り扱っていないので、より詳しく知りたい方は最下部の参考文献の原本を読んでみてください。
2008年度京都市立芸術大学美術学部総合芸術学科卒業論文『 京友禅を中心とする呉服産業に関する一考察-その現状、行方、課題、及び試案- 』より
京都市立芸術学部美術学部総合芸術学科 森真琴 2009
目次
第1章 着物
第1 節 着物に関連する用語の整理
着物と一言で言っても、それには様々な種類があり、さらに着物だけでなく、和服、呉服などといった呼称もあって複雑である。また現在着物と呼ばれているものは、かつては小袖と呼ばれており、その概要をおさえておくこともまず、必要と思われる。そこで着物に関連する用語を整理する。
着物
着物という語が何を意味するかということは、大変難しい。服飾史の本には、細分化された服飾用語に関する考察が多くなされているが、着物という大きな概念に関する詳細な考察はなかなか見あたらない。そこでここでは、『原色染織大辞典』[1]の記述をひいておく。
これによると、着物とは、広義には身体に着る物、すなわち衣服を意味する。また狭義には、洋服に対する和服全般を指す。この場合年齢、男女、種類を問わない。さらに狭義に、和服の中で、特に長着[2]形式のものを指す場合がある。いわゆるワンピース形式で、身体に巻き付け帯を締めて着る表着を、羽織や襦袢などと区別していう。
また、高田氏によると、「きもの」という言葉がはじめて文献に見られるのは、鎌倉時代、十三世紀中頃の『古今著聞集(ここんちょもんじゅう)』である[3]。このころの「きもの」は特定の衣服を指す言葉ではなく、衣服一般を指し示す言葉として使われていたと推測されている。
和服
上記の辞典によると[4]、洋服などの外国の衣服に対して、日本在来の衣服を、和服と呼ぶ。これは一般に着物と呼ばれるもので、江戸時代に完成された小袖を中心とした服装で形成される。その種類には長着、羽織、帯、袴、襦袢などがある。方形の布を直線的に縫い合わせるという構成上の特徴がある。
呉服
再度上記の辞典を引用すると[5]、一般に和服用の織物を総称して呉服という場合と、麻や木綿の織物を太物というのに対して、絹織物を指して呉服という場合がある。
以上、辞書から着物、和服、呉服の意味を拾い上げてみた。これらをまとめると、着物という語は大きく分けて三段階の意味をもっていることがわかる。最も広義には、着る物全般を指し、狭義には、和服一般を指し、最狭義には、和服のうちワンピース状の長着を指すと言うことができる。また和服という語は、洋服に対する語であり、日本の衣料と言うニュアンスが強いこと、さらに呉服という語は、衣料形態を指す語というよりもむしろ、それを構成する織物(特に絹織物)を強く意識した語であるということができる。
第2節 着物の変遷~小袖の成立から着物~
次に、着物の前段階にあった、小袖に関して、時代を追いながら見てゆく。
平安時代の小袖
小袖は、平安時代の公家の服飾としてまず現れた。高田氏によると、小袖とは袖の面積が小さいという意味ではなく、袖口が小さいことを指している語である[6]。小袖は袖口が小さく、円筒状の袖が腕を包む、筒袖といわれる袖をもつ上半身を包む服であった。公家は二種類の小袖を持っていたと考えられる[7]。一つは、礼服(らいふく)の一具としての盤領(あげくび)[8]の小袖であり、もう一つは、朝服の下着としての小袖である。
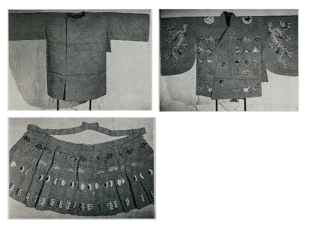
第一の小袖は、公服制度の中で最高位の服で、大儀の際に天皇・皇太子以下官人が用いた礼服の一部であった。大袖の衣の下に、衿まわりが丸い盤領(あげくび)で、腰までの丈の小袖が、内衣として着用された[9]。これを彷彿とさせる作例として、佐藤氏は、孝明天皇所用の礼服をあげている(図1)。現在確認できる書物の中で、小袖という言葉の初見は平安時代、十世紀中頃に源高明が書いた『西宮記(さいきゅうき)』であるとされている。『西宮記』に記された小袖は、大袖の下に着用されたものであることから[10]、細い筒袖のものであったと推測される。
第二の小袖は、朝服の下に肌着として着用された。朝服は、宮廷官人の通常の官服である。平安時代に入って公家貴族の生活全般にわたって唐風の単なる模倣が次第に国風化していく中で、調達に多額の費用を要する礼服はめったに使われなくなり、より実用的な朝服が多く着用されることになった。そして平安時代後期には朝服を基本とした国風化した束帯(男)唐衣裳姿(女)に代表されるいわゆる襲装束が成立した。襲装束の各種の衣は全般に寛潤で丈も長く袖も大きい広袖であり、防寒上に問題があり、袖口の詰まった下着を必要とした。こうして公家貴族の装束の下に小袖が着られ始め、それが一般化したのがほぼ十世紀末から十一世紀初頭であった[11]。
大袖の下着とされたこのような小袖が描かれた例として、佐藤氏は「粉河寺縁起絵巻」や「平治物語絵詞」の描写をあげている(図2、3)[12]。これらには、垂領[13]の白い小袖が下着として描かれている。装束の下の小袖は始めのうちこそ筒袖であったが、次第に袖に丸い小さな袂を付けた形に発展し、平安時代の末期には丸い袂のある小袖が、装束の下に定着した[14]。

旅立つ馬上の長者の妻に市女笠を差し出す女の手元に小袖が見られる。「粉河寺縁起絵巻」第五段

具足を背にした家居の藤原信頼。「平治物語絵詞」六波
鎌倉・室町時代の小袖
公家や庶民の間では、平安時代より一枚着の筒袖の衣服が用いられていた。これを手細という[15]。手細は、公家が肌着として着ていた小袖と形状が酷似していた。高田氏によると、鎌倉時代には武家がこのような同形の着物を、公家の名称にならって小袖と呼び始め、それから若干遅れて庶民の間にも、自分たちが着ていた同じような形の着物を小袖と呼ぶ者が出てきたと考えられる[16]。
小袖が現代の着物と直接通じるものとしての性格を持つようになったのは室町時代後期(戦国時代)のことで、その頃になると下克上や治安の低下などから、袖が小さく活動的な小袖が表着として武家の正装に採用されるようになった。鎌倉時代以降実質的な支配者になった武家であるが、前支配者の公家からの権力の継承を人々に印象付けるため、重要な場では公家的な服飾をつけることが多かった。私的な場では絹小袖の上に直垂など武家独自の衣服[17]を身に付けた。小袖が大袖に代わって支配階層や富裕階層の衣服の主流になったため、庶民の衣服も合わせて、世の服装は小袖中心の様相を呈するようになった。なおその流れを決定づけたものは政治、文化の一大転機である応仁の乱と言われている。そしてこのころから、庶民の間でも、彼らが長らく用いてきた衣服を武家同様に小袖と呼ぶようになったと推測される。
室町時代には小袖の形態と仕立ては、ほぼ現在の着物と同様になっていた。平安時代には小袖はそのほとんどが筒状の細い袖を持った衣服であったと考えられるが、袖口の大きさはほとんど変わらないものの、時代とともに袖の大きさは増し、次第にゆったりしたものになった。室町時代には袖はさらに大きくなり、現在の着物のイメージに結び付くほどになった。
桃山・江戸時代の小袖
桃山時代にポルトガル宣教師が記した報告書[18]に、小袖を指す言葉として着物が見られる。着物という語が衣類一般を指して用いられるのではなく、特に小袖を指して用いられ始めていたと推測される。このように桃山時代にかけて、今日の着物に直接連なる小袖の形式が完成され、その後、江戸時代になって生地や加飾装飾・意匠などに時代的変化や時々の流行を生み出した。 江戸時代も後期を過ぎると公家の間でも儀式以外では小袖を着るのが通例となった。また小袖自体の袖は平和な時代の中で華美になり巨大化して振袖が誕生、そのため小袖と言う名称自体が実態に合わなくなり使われなくなってしまった。現在では小袖というと束帯や十二単など宮廷装束の下着を指す。化政文化の頃、江戸では褄模様といわれる足下に模様を入れることが流行り、その後留袖の原型になる江戸褄[19]が生まれた。また、庶民の小袖から身八つ口[20]が生まれた。留袖にしろ、身八つ口にしろ、現在の着物の原型はこのころの庶民の着物に端を発する物が多い。
明治以降のきもの
明治時代に入り、欧米文化模倣の一環として服装の洋風化が始まり、それまでの衣服とこれらが併存する状況が生じた。当時、指導的立場にあったのは華族や貴族、すなわち江戸時代後期における公家や大名たちである。彼らは江戸時代に大袖を着る機会があった人々である。彼らは欧米諸国に対し、近代化した日本をアピールするために洋装化を急いだ。そのため、大袖を着る人が急激に激減し、対概念としての小袖という言葉の存在意味がなくなった。しだいに小袖系の和装には桃山時代から江戸時代にかけて小袖と同義語として用いられている着物という言葉、新しく入ってきた洋装に対しては洋服が用いられるようになった。文明開化といっても実際には明治の末期までは上流階級の女性や公職に関わる男性を除き、一般の服飾に関しては江戸時代の小袖系の衣服が主流をなしていた。大正時代になり洋装が着物をややしのぐほど普及してくると洋服を着物とほぼ同等の存在とみるようになり、洋服に対して和服という言葉が使用されるようになった。
昭和に入ると学生服などにも採用されるようになり、この頃から大人から子供に至るまで洋服が普及するようになった。戦時下における国民服を経て、その後の経済成長期の中で既製服生産の発達により洋服は一段と普及した。昭和三十年代になると着物を一人で着られなくなる女性が多くなり、着物姿自体が稀なものとなり、和服はいわゆる民族衣装との認識が強まった。現在では着物は職業的なものを除くと伝統行事の際の晴れ着、または趣味的な衣服のみとして用いられるようになっている。
これまで見てきたように、小袖は、現在の着物に連なる共通点を持っている。具体的に言えば、身頃と袖を持ち、前身に襟と衽を加えた垂領(たれくび)式の衣服である[1]。本論(この卒業論文内における扱う着物と呼ばれるもの)においては、これらの特徴を引き継いで現在もその形態を有するものを、着物と定義づけることとする。
卒論の続きが気になる方はこちらからご拝読ください。第2章以降は京友禅のこととか業界のことなので、服飾史についてはこれといって触れていません。10年以上前の拙い学生時代の論文のためいろいろ未熟な点が多いです。特に分析やら提言部分のクオリティが10年ぶりに読むと低い。。。より詳細に知りたい方は卒業論文中の参考文献等をあたってみてください。
※卒業論文の無断複製 転載 配布行為はご遠慮ください。
※なんとなく思いつきで全文公開にしてるので、気が変わったら卒論全文の方は消すかもしれないです。
※久々に引っ張り出したので、もしかしたら最終稿じゃない可能性があります。(汗)
参考文献
[1] 板倉寿郎、 1977、 P. 308
[2] 長着とは農村、漁村で家にいる時や仕事を終えた夜間などに着る丈の長い着物対丈で筒袖やもじり袖が普通。縞や無地の紺木綿を用い、単・袷・綿入れなどに仕立てる。山口県萩市や青森県下北地方の呼称。一般には裾までの和服をいう。 板倉寿郎、 1977、 P. 778
[3] 高田倭男、 1995、 P. 118 は、この文献の巻第二十をあげている。「下臈のきる手なしといふ布着物きて」とあり、これは「身分の低い人が着る『手なし』という麻の『きもの』を着て」という意味で、着物という語が出てくる。
[4] 板倉寿郎、 1977、 P. 1211
[5] 板倉寿郎、 1977、 P. 419
[6] 高田倭男、 1995、 P. 149
[7] 高田倭男、 1995、 P. 149
[8] 袍や狩衣のように円い作りの衿。身頃の左右を合わせ、首の付け根の回りに沿って刳り、細幅の領をつける。一方の肩下の所で長紐または結び紐の方法で留める。奈良時代の朝服、平安時代の束帯や直衣など男子の主要な上衣はこの作りである。 板倉寿郎、 1977、 P. 19
[9] 佐藤泰子、 1992、 P. 62
[10] 巻十七 天皇礼服の条に「次著小袖大袖」と記述されている。
[11] 河上繁樹、 1994、 P. 45
[12] 佐藤泰子、 1992、 P. 62
[13] 袿や小袖のように領の両端が全身で低く、垂れ下がり、着用のとき、左右を前で斜めに重ね合わせる形のもの。盤領に対して言う。男子は奈良時代の礼服、鎌倉時代以降の直垂・大紋・素襖など。女子は装束や庶民の衣服などをこの形で作った。現在の和服に同じ。 板倉寿郎、 1977、 P. 673
[14] 平安後期(院政期)から鎌倉時代初期には貴族の間に爆発的な小袖ブームが訪れ袿(うちぎ)の代わりに豪華な織物で仕立てた小袖を何重にもまとうことが流行するが、余りにもお金がかかるためにしばしば禁止令が出された。そのため、室町時代まで貴族や武士などの上層階級では小袖は下着の扱いのままであった。
[15] 庶民の手細は模様のない白地のものが多かったが、上衣として用いたこともあり、無地染めや、簡単な絞り染めをつける場合もあった。
[16] 高田倭男、 1995、 P. 148
[17] 直垂や素襖は武家独自の衣服であるが、形状は大袖に分類されるものでこれらも公家服飾の名残を残すものと言える。
[18]天正五年(1577)頃に来日したポルトガルの宣教師ジョアン・ロドリーゲスが残した資料の中に「この王国全体を通じて人々が身分の上下男女の別なくつねに着ているおもな衣類は着る物もしくは着物と呼ばれる。それは部屋着風の長い衣類であって、現在では上品さと美しさを保つためにかかとまでの長いものを用いるけれども、古風に従ったものは下脚の半ばすなわち向こうずねの半ばまで届くのである。幅広い袖はポルトガルのサイーニョ(裾のない円筒形式の襦袢)風のもので、腕の半ば過ぎまで届くが、それからからさきはむき出しになる。」(『大航海時代叢集』第一期第九・十巻 岩波書店、1969・70)との記述がある。
[19]江戸褄模様の略。小袖の文様付様式の一つ。本来は、長着の裾の褄に近い部分に文様を配置したもの。江戸後期に発祥し、今日一般に黒地に五紋を染め抜き、江戸褄模様を施した留袖を指す。現在も既婚者の礼服として用いる。留袖模様ともいう。 板倉寿郎、 1977、 P. 141
[20]和服の部分名称。女物・子供物の和服の袖付下で脇に口をあけた部分。これによって手の運動による袖付止りのほころびを防ぐ効果がある。女物のあきは13~15cm。かつては主に関東地方で用いた呼び名。身明け・脇明き・身人形ともいう。 板倉寿郎、 1977、 P. 1043
板倉寿郎 『原色染織大辞典』 淡交社 1977
河上繁樹 『公家の服飾』 日本の美術no.339 至文社 1994
佐藤泰子 『日本服飾史』 建皐社 1992
高田倭男 『服装の歴史』 中央公論社 1995
谷田閲次『 日本服飾史』 光生館 1989
長崎巌 『小袖からきものへ』 日本の美術no.435 至文社 2002


